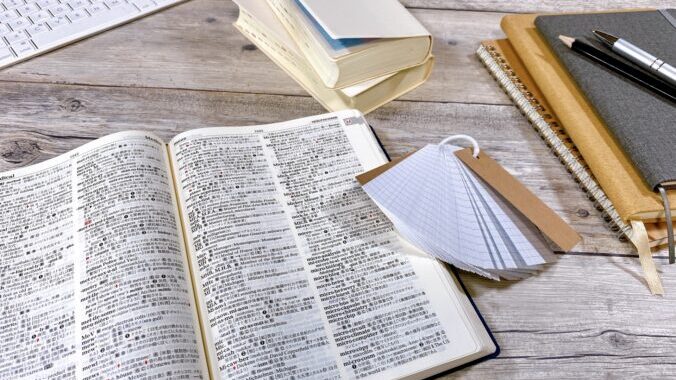-

【用語解説】せん断強度
せん断強度とは、土がせん断破壊に抵抗できる限界の強さを示す指標です。地盤の安定性や支持力を評価するための基本的な力学特性で、斜面安定計算や擁壁設計などに用いられます。 せん断強度の概要 せん断強度は、土に作用するせん断応力に対して、破壊に... -

【用語解説】三軸圧縮試験
三軸圧縮試験とは、円柱状の供試体に拘束圧を与えた状態で軸方向に圧縮荷重を加え、土のせん断強度特性を求める室内土質試験です。内部摩擦角Φや粘着力cを設定するための代表的な試験方法です。 三軸圧縮試験の概要 三軸圧縮試験では、供試体に側圧として... -

【用語解説】粘着力c
粘着力cとは、土のせん断強度を構成する要素の一つで、拘束圧が作用しない状態でも発揮されるせん断抵抗成分を示す値です。内部摩擦角Φと組み合わせて、地盤のせん断強度を表すために用いられます。 粘着力cの概要 粘着力cは、モール・クーロンの破壊基準... -

【用語解説】内部摩擦角Φ
内部摩擦角Φとは、土のせん断強度を表す指標の一つで、拘束圧(有効応力)とせん断抵抗力の関係を角度として表したものです。安定計算や支持力計算など、地盤の力学的評価に用いられます。 内部摩擦角Φの求め方 内部摩擦角Φは、三軸圧縮試験や一面せん断試... -

【用語解説】事前協議
事前協議とは、開発行為や宅地造成、構造物設置などを行う前に、行政や関係機関と計画内容についてあらかじめ協議する手続きを指す実務上の呼称です。特定の法律で定義された正式用語ではありません。 事前協議の概要 事前協議は、申請や許可の前段階とし... -

【用語解説】キャスポル
キャスポルとは、簡易支持力測定器のことです。加速度計を内蔵したランマーを地盤に落下させ、衝撃加速度(インパクト値)から地盤反力係数やコーン指数などを推定し、施工管理や支持力確認に用いられます。 キャスポルの概要 画像引用元:株式会社マルイ... -

【フリーソフト】平板載荷試験の荷重計画
平板載荷試験の荷重計画を作成するツールです。荷重段階は5~8段階に対応しています。また、長期と短期の安全率に対応しています。 アナログメーターを想定し、荷重段階は整数に切り上げるようにしています。 品質管理試験の効率化に是非ご活用下さい。 平... -

【用語解説】標準貫入試験
標準貫入試験とは、地盤の硬さをN値として評価するための地盤調査試験です。ボーリング調査とあわせて実施され、建物の基礎設計や宅地造成の検討に広く用いられています。 標準貫入試験の概要 標準貫入試験では、63.5kgのハンマーを76cmの高さから自由落下... -

【用語解説】平板載荷試験
平板載荷試験とは、地盤上に円形または角形の載荷板を設置し、実際に荷重をかけて地盤の支持力や沈下特性を確認する試験です。地盤の強さを実測で評価できる試験として用いられます。 宅地造成工事では主に建築物の基礎や擁壁基礎地盤の品質確認として使用... -

【用語解説】ボーリング調査
ボーリング調査とは、地盤に孔を掘削し、地下の土質や地層構成を調べる地盤調査方法です。建物の基礎設計や宅地造成の検討において、最も基本となる調査の一つです。 ボーリング調査の概要 ボーリング調査では、地盤に孔を掘りながら、土の採取や各種試験... -

【用語解説】サンプリング
サンプリングとは、地盤調査において地中の土を採取する作業のことです。土質の確認や各種試験を行うための基礎資料として用いられます。 サンプリングの概要 サンプリングでは、ボーリング調査などにより地盤から実際の土を取り出します。 採取された土は... -

【用語解説】盛土等規制法
盛土等規制法とは、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の通称です。盛土や切土による災害を防止することを目的とした法律で、全国一律の規制が設けられています。 盛土等規制法の概要 盛土等規制法では、一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積について、事... -

【用語解説】29条
29条とは、都市計画法第29条のことを指します。一定規模以上の開発行為を行う場合に、都道府県知事等の許可が必要であることを定めた条文です。 29条の概要 都市計画法第29条では、宅地造成などの開発行為を行う際は、原則として事前に開発許可を受けなけ... -

【用語解説】32条
32条とは、都市計画法第32条のことを指します。宅地造成や開発行為を行う際に、管理者との協議や同意が必要となることを定めた条文です。 32条の概要 都市計画法第32条では、開発行為により影響を受ける公共施設について、その管理者とあらかじめ協議し、... -

【用語解説】柱状図
柱状図とは、地盤調査の結果を深さ方向に整理して示した図のことです。土質の種類や層の構成、地下水位などを視覚的に把握するために用いられます。 柱状図の概要 柱状図は、地盤調査によって得られた情報を深さごとに縦方向へ並べて表現したものです。 一... -

【用語解説】支持力
支持力とは、地盤が建物や構造物の荷重を支えられる能力のことです。基礎設計や宅地造成の検討において、地盤の安全性を考えるうえで重要な概念です。 支持力の概要 支持力は、地盤が沈下や破壊を起こさずに支えられる限界の力を指します。主に地盤調査結... -

【用語解説】N値
N値とは、地盤の硬さを表す指標です。標準貫入試験により求められ、建物の基礎設計や宅地造成の検討で広く用いられています。 N値の概要 N値は、標準貫入試験においてサンプラーを地盤に30cm打ち込むのに必要な打撃回数を示した数値です。 数値が大きいほ...